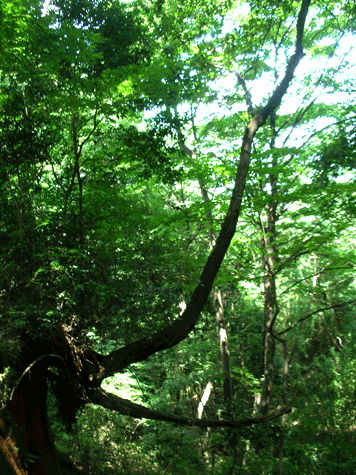稲城南山とその周辺
稲城南山と多摩丘陵 <考察編>
4.崖崩れを防ぐ樹林の力
砂層の崖が崩れる原因
砂層の崖が崩れる原因としては、
・ 雨水による表面の浸食、
・ オーバーハングしていて、下に支える物がないとき、
・あまり固まっていない崩れやすい砂層で、斜面の傾きが急すぎるとき、
・ 大量の雨水の浸透と地下水の滞留による滑りやすい面の形成、
・ 沢などの水の流れがあるときは、水の流れによる浸食、
・ 地震
などが考えられます。
一方、崖が崩れるのを防いでいる自然の力もあります。樹林の存在です。
崖が崩れるのを防いでいる樹林の存在
(1)樹林は雨水の力を和らげる。

 樹木や下草、落ち葉や腐植土があると、雨水は木の葉や枝、下草、フカフカした腐植土を濡らし、そこに留まり、根によって吸収されて植物を潤したり、小さな虫や種々の微生物の活動を支えたりし、晴れれば徐々に蒸発します。
樹木や下草、落ち葉や腐植土があると、雨水は木の葉や枝、下草、フカフカした腐植土を濡らし、そこに留まり、根によって吸収されて植物を潤したり、小さな虫や種々の微生物の活動を支えたりし、晴れれば徐々に蒸発します。
一挙に地下に浸透することはありません。徐々に地下に浸透し、分散していきます。
稲城南山には広大な根方谷戸があります(写真左上)。
そこで降った雨はふもとの妙覚寺付近では小さな溝のような根方谷戸川の流れ(写真左下)になっています。
大量の雨水は樹林帯に蓄えられたり、地下の砂層に徐々に浸透して水を通しにくい地層に達すると、その地層の傾いている方向に地下水となって流れたりします。
根方谷戸では沢に大量の水が流れ込むことはあまりないのです。
(稲城南山の地下にJRの貨物線のトンネルがあるので、かなりの地下水がそのトンネルに流れ込んでいるのかも知れません。)
樹林がないとどういうことになるのか。
都会では森林は少なく、大雨が降ると一挙に低いところに流れが集中し、予想もしていない事故を起こします。
集中豪雨で都市の河川が一挙に増水し、急流となり、親水公園で遊んでいた保育園児が流されたり、下水管が一挙に増水し、下水管工事をしていた作業員が流されて行方不明になるということも起こりました。
集中豪雨のため、水がどぶからあふれたり、舗装された坂道の下の方で水位が高くなり人が歩けなくなったり、地下室に水が流れ込んで、水圧で出口のドアも開かない危険なことになったり、ということも起こっています。
(2)樹林では植物の根が互いに絡み合って、強固なマットを作っている。
樹木や草の根は水分や養分を求めて横方向にも広く伸び、互いに絡まり合って、その結果山林の表面は根っこの絡まったマットになっています。
根っこの絡まり合ったマットは強靱です。その強靱さは、崖地の木を見ると理解できます。

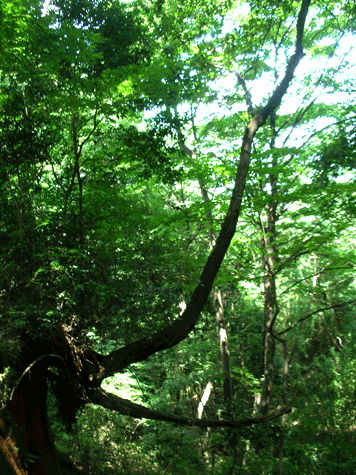
崖地の木 稲城南山の自然の崖地に生えている木。林道の脇に崖が食い込んでいる場所にあります。雨水による浸食で、崖は少しずつこの木の根元を通り越して成長していると思われます。根元の下に土はなく、向こう側が透けて見えています。
この木の幹は根元近くではぶら下がっている根株にほぼ垂直に伸びており、途中から斜め上に向かって長く伸びています。
このことから、 この木は崖にぶら下がった状態になった後も、さらに長い年月をかけて成長を続けていると考えられます。
写真には写っていませんが、右の写真の右上の先端よりも、さらに上空の方に向かって枝がのびて、広く枝葉を広げています。
この木の重量は相当な物だと思いますが、木の根の力で崖にぶら下がって持ちこたえています。
木の根が作るマットの力・・・この木が崖の下に落ちていかないのは、この木だけの根の力ではなく、周囲の樹木からも伸びている無数の根が互いに入り乱れ、絡まり合って作られている根のネットワーク、根のマットの力によるものだと思います。
根が作るマットの力・・・小さな草や木を引き抜こうとしても、自然の樹林や草原に生えている草木はなかなか引き抜くことは出来ません。その様な体験を持っている人も多いと思います。
この崖地の木、自然について、さまざまなことを考えさせてくれます。
稲城市や東京都の天然記念物に指定出来ないでしょうか?
(2008年8月記/8月13日一部追記、
8月16日、南山の人工の崖については別項にしました。)
本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム
| さまざまな報酬パターン
| 共有エディタOverleaf
 業界NO1のライブチャット
|
業界NO1のライブチャット
|  ライブチャット「BBchatTV」 無料お試し期間中で今だけお得に!
ライブチャット「BBchatTV」 無料お試し期間中で今だけお得に!
 35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV]
| 最新ニュース
| Web検索
| ドメイン
| 無料HPスペース
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV]
| 最新ニュース
| Web検索
| ドメイン
| 無料HPスペース

 樹木や下草、落ち葉や腐植土があると、雨水は木の葉や枝、下草、フカフカした腐植土を濡らし、そこに留まり、根によって吸収されて植物を潤したり、小さな虫や種々の微生物の活動を支えたりし、晴れれば徐々に蒸発します。
樹木や下草、落ち葉や腐植土があると、雨水は木の葉や枝、下草、フカフカした腐植土を濡らし、そこに留まり、根によって吸収されて植物を潤したり、小さな虫や種々の微生物の活動を支えたりし、晴れれば徐々に蒸発します。
 樹木や下草、落ち葉や腐植土があると、雨水は木の葉や枝、下草、フカフカした腐植土を濡らし、そこに留まり、根によって吸収されて植物を潤したり、小さな虫や種々の微生物の活動を支えたりし、晴れれば徐々に蒸発します。
樹木や下草、落ち葉や腐植土があると、雨水は木の葉や枝、下草、フカフカした腐植土を濡らし、そこに留まり、根によって吸収されて植物を潤したり、小さな虫や種々の微生物の活動を支えたりし、晴れれば徐々に蒸発します。